わたのおはなし
綿の歴史
日本に初めて綿が伝来したのは8世紀末とされています。その根拠は、『類聚国史』にあります。そこには延暦18年(799年)に、崑崙人が三河国に漂着して綿種を伝え、その翌年に朝廷は綿の種子を紀伊などの国々に配り、試植させたことが記されています。
『類聚国史』とは、編年体である六国史(日本書紀、続日本紀、日本後紀、続日本後紀、日本文徳天皇実録、日本三代実録)の記載を中国の類書にならい分類再編集したもので、菅原道真の編纂により、892年(寛平4年)に完成・成立した歴史書です。史料価値は高く、これが日本に綿が伝来した最初の記録とされています。
しかし、このときに各地に植えられた綿の種子は定着することなく途絶えてしまいます。
その後、日本にいつ頃からどのようにして綿製品が伝来し、国内での栽培が行われるようになったかについては、まだ諸説あり、研究段階にあるようです。
そこで、以下の項目については、おもに永原慶二氏の『新・木綿以前のこと-苧麻から木綿へ』(中公新書963、1990年発行)と「綿作の展開」『講座・日本技術の社会史』第3巻「紡績」(日本評論社、1985年発行)所収に拠っていることを最初に明記しておきます。
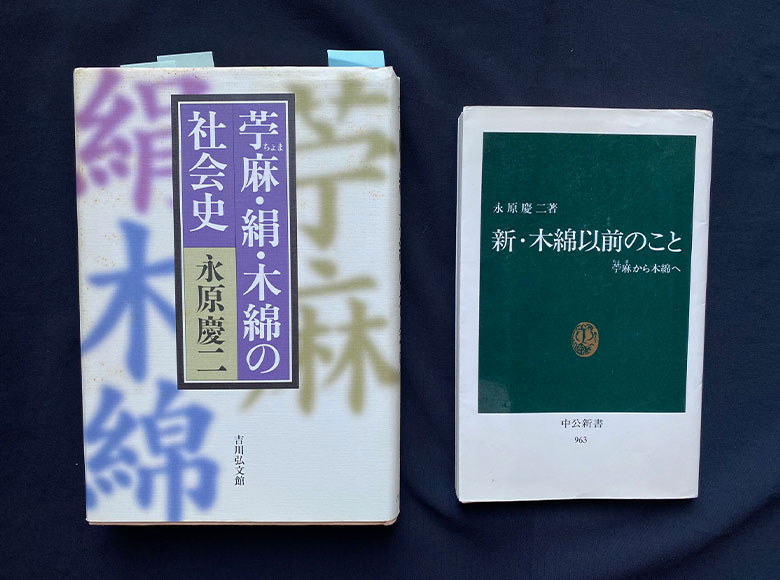
輸入木綿の時代
文献上に「木綿」が現れはじめるのは鎌倉時代以降(いわゆる現在の[もめん]の意味で用いられる例。絹を指すと思われる奈良時代の[ゆう]の例は除く)で、もっとも古い例として1204年の高野山金剛峯寺関係の記録が残っています。寺院や寺僧関係が使用した繊維品の中に、綿が用いられるようになったとも考えられます。しかし、この頃の「木綿」がそのまま後の草木綿と共通するものかどうかは確定が難しく、史料上、いわゆる「木綿」が散見されるようになるのは14世紀中頃以降、すなわち南北朝、室町期に入ってからです。
もちろんこの頃の木綿はすべて輸入品であり、1406年に室町幕府が朝鮮国王に派遣した使節たちに与えられた賜物の中にも、青木綿や綿子が見えます。そして、この頃から朝鮮木綿に対する日本側の関心と需要が急速に高まっていきました。
室町時代中期に入って日本側の木綿需要が急激に高まりだしたのは、それが兵衣として抜群の性能を持つことが認識されるようになったからであると考えられます。応仁の乱(1467-1477年)はその状況に拍車をかけ、幕府をはじめ各地の戦国大名たちは競って朝鮮から木綿を輸入するようになります。
そして、朝鮮国内で木綿が深刻な品不足に陥ると、朝鮮側は木綿価格を引き上げたりしながら輸出制限をかけるようになり、日本ではその対応策として中国からの輸入をはじめるようになります。16世紀の後半には輸入木綿では中国木綿が朝鮮木綿を上回る水準に達していたとみられています。
こうして、木綿は当初、貴族社会においては高級布地として珍重される一方、民衆の衣料素材としてというより、軍事上必要不可欠な素材(兵衣、幔幕、火縄等)として急速に広まっていったと考えられます。
(『新・木綿以前のこと』54-70頁。前掲「綿作の展開」71-73頁参照)

国産木綿の時代
木綿関係資料で、国内生産を確証するもっとも古い史料として1494年に越後の上杉房定が毛利重広に宛てた安堵状と、「文亀二年(1501年)四月十九日」という年月日が記されている武蔵国越生郷上野村聖天宮社の棟札があります。前者には「みわた(実綿)」の文字が見られ、後者には「木綿一反」を奉納したことが記されています。そして、この頃から各地に綿作を伺わせる文献史料が散見されるようになり、こうしたことから15世紀末~16世紀中頃が日本における綿作、綿業の開始期と考えられます。
しかし、どの地方から綿作がはじまったのかについては実はよくわかっていません。一般には三河発祥地説が有名ですが、延暦年間の崑崙人漂着の記事はそのまま綿作に結びつくものではなく、史料的には三河地方より早くに綿作が行われていたことを示す例が各地にあります。三河地方も早くから綿作が行われていた有力な産地であったことは間違いないとしても、実際はそれと平行して広く各地でほぼ時期を同じくして栽培が行われるようになったのではないかと考えられます。
そして、その後は綿作、綿織物の国内生産は比較的短期間のうちに東北の一部をのぞいてほぼ全国に広まり、自給的目的による栽培とともに、商品作物としての栽培が行われるようになっていきました。
こうして、江戸時代以前には西は九州から東は関東に至るまで、おそらくほとんどの地域で綿栽培、木綿織は展開していたと考えられ、その後、江戸時代をとおして深く庶民の生活に浸透し、その製品の流通は産業構造や経済史的にも大きな影響をあたえることになっていきました。
(『新・木綿以前のこと』72-106頁。前掲「綿作の展開」74-88頁参照)
「おそらく日本の国内における木綿栽培は、九州からはじまったであろう。しかしそれはかつて稲作が北九州から逐次東方に広まっていったのと同じような足どりをとったわけではあるまい。そうではなく、ほとんど同時的に、各地に併行して種子が伝わり、そこここで綿作が行われるようになったのではないか。その際、北陸・東北方面が立ちおくれていたことは事実だが、全体として国内木綿の栽培の開始と広まりを、江戸時代前期中心に見る通説的理解は訂正される必要がある。実際はそれよりも早く、16世紀中における展開の度合いを、これまでよりは大きく評価すべきであると考えられるのである。」
(『新・木綿以前のこと』104頁)

木綿以前の時代
木綿が庶民にとって身近な衣料素材として普及するようになる17世紀初まで、庶民が身につけていた素材はおもに麻でした(絹も古代からありましたが、庶民が日常的に身につけることができるものではありませんでした)。ただし、それだけではありません。古代、中世を通じて民衆衣料の素材とされたのは麻のほかに藤や葛、楮(こうぞ)などからとった繊維もありました。『日本書紀』などの古代の文献に「木綿(ゆふ)」とあるのは、現在の木綿ではなく、楮からとった糸と考えられています。
とくに麻の原料となる植物は苧麻(ちょま)と呼ばれ、イラクサ科に属する多年草で、山野に自生し、至る所で手に入ったそうです。それを畑に植えて栽培し、主要な衣料原料としていました。現代の感覚からすればと「麻」には高級感がありますが、夏ならともかく、冬の素材としては不向きです。しかし、木綿(もめん)がなかった時代にはそれしかなかったわけですから、寒い季節には何枚も重ね着をして寒さをしのぐしかありませんでした。
日本に木綿製品が伝来するのは14世紀以降ですが、なぜ朝鮮や中国からもっと早くに伝来しなかったのか。素朴な疑問が湧いてきます。実は朝鮮半島に木綿の種子が伝来したのは、14世紀後半の高麗末期であったようです。高麗の恭愍王(1352-1374在位)の13年、元朝に送られた使者が、帰路、中国で木綿を見てその種子を持ち帰ったのが発端となり、それから10年ほどのうちに朝鮮国内に広まったといわれています。
また、中国で木綿の栽培と綿布の生産が行われるようになるのは唐の頃であり、宋末から元初の頃には江南にまで広まっていたものの、本格的に木綿栽培が発展期に入るのは14世紀末から15世紀初頃であったようです。
(『新・木綿以前のこと』58-63頁参照)

「おあむ物語」 麻から木綿への転換期
麻から木綿への過渡期を象徴する事例に「おあむ物語」に記された女性の昔語りがあります。その女性は「おあむ(御庵)」と言い、石田三成に仕えた知行300石の侍の娘です。「さて、衣類もなく、おれが十三の時、手作のはなぞめの帷子一つあるよりほかには、なかりし。そのひとつのかたびらを、十七の年まで着たるによりて、すねが出て、難儀にあつた。せめて、すねのかくれるほどの帷子ひとつ、ほしやと、おもふた。此様にむかしは、物事ふ自由な事でおじやつた。…今時の若衆は、衣類のものずき、こころをつくし、金をつひやし、…沙汰の限りなこと」。
おあむは寛文年中(1661~1673)に八十余歳で亡くなっていることから、1590年前後の生まれと考えられます。この女性は、娘盛りの十三歳から十七歳まで、麻の着物1枚しか与えてもらえず、ほぼ4年間それを着続けたため、成長するにつれて臑(すね)が露出して困ったというのです。そして、当時の自身の生活と比べて、最近の若者が木綿の着物を贅沢に着ているのが許せない、と。
麻から木綿への転換は、衣料革命であったとも言われます。同じ糸でも、麻糸を績むののには一日で七グラム(2匁足らず)、木綿糸の場合は一日四十匁を紡ぐことができたと言いますから、これだけで約二十倍の違いです。糸の量はそのまま反物の量に比例します。その上、木綿は麻とくらべて色の染まりもよく、加工も容易でしたのので、綿の栽培と木綿織りがひろまることで、庶民の衣生活が格段に向上したことは容易に想像がつきます。
(『新・木綿以前のこと』2-5頁。42-43頁参照)

各地特産の綿織物
綿の栽培をしていた農家が、自家用に糸を紡ぎ機織りをする一方で、それを商人が買い取ることで農家は副収入を得ることができるようになります。木綿の需要はいくらでもあり、次第に織物の技術もデザインも洗練されていくようになり、やがて、全国各地でさまざまな綿織物が生み出されていきます。
藩によっては、それを藩の名産品として集約することで財政の立て直しに成功する事例も出てきます(一例として、姫路藩など)。
商人によっては、地方から江戸に進出して大成功を収めた事例もあります(一例として、松阪木綿の三井越後屋)。
また、幕末から明治時代にかけて外国から安くて良質な紡績綿糸が手に入るようになると、化学染料で染色した糸を用い、鮮やかな木綿布を生み出し、全国に販路を広げた地域特産品も生まれてきました。
日本の綿織物の主な産地は遠州(静岡)、三河(愛知)、泉州(大阪)であり、これらは「日本三大綿織物産地」とも呼ばれていますが、その背景はさまざまです。
そして、これらの地域以外にも福岡県の博多、小倉、兵庫県の播州、愛知県の知多、栃木県の真岡、福島県の会津木綿、富山県の福野縞、岐阜県の美濃縞、愛媛県の伊予絣、福岡県の久留米絣、広島県の備後絣、鳥取県の弓浜絣、群馬県の中野絣、奈良県の大和絣など、全国各地に特色ある綿織物の産地、織物が存在します。現在も各地域で伝承文化の保存継承に取り組んでおられる手織りグループには、それぞれの地域の歴史が詰まっています。ぜひ一度、ご自身の地域の綿作と織物の歴史を繙いてみてください。

